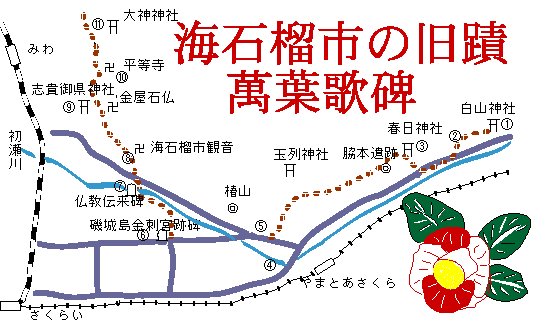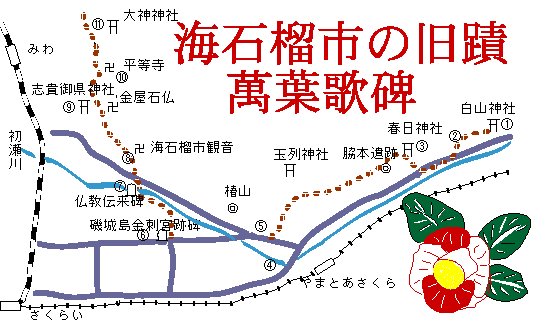|
大神神社
三角錐の秀麗な山容を持つ三輪山を御神体として、本殿を持たず拝殿のみの古の伝統が残る神社。記紀をはじめとする数々の神話・伝説を伝える。祭神は大物主神であるが、水に関わる自然崇拝がその信仰の源といわれている。
平等寺
大神神社の元神宮寺。明治初年の廃仏毀釈によって一時衰えたが、のちに復興した。鎌倉時代に真言宗の別所として開かれたのが、寺の始まりといわれる。
志貴御県坐神社(しきのみあがたにますじんじゃ)
県とは、大化改新以前の制度で皇室の直轄領地という有力な説がある。磯城県主の祖神、天津饒速日命(あまつにぎはやひのみこと)を祭神とする。境内には、「崇神天皇磯城瑞籬(しきみずがき)宮跡」碑が建つ。第十代天皇、崇神天皇は初期大和王権(三輪王朝)の王として実在したことは確実視されている。
金屋石仏
もともとは三輪山中腹に安置されていたが、明治初年の神仏分離によりこのあたりに移されたという。高さ2メートルあまりの古墳石棺を利用して、釈迦如来と弥勒如来を彫る。制作年代については、平安初期から鎌倉に至るまで各説ある。重要文化財指定。
海石榴市観音
地区の人たちが管理する小さなお堂に石仏が二対安置されている。向かって右が、長谷寺式観音の特徴を持つ十一面観音。左は聖観音である。いずれも元亀(1571〜1572年)の銘を持つ。初瀬川の岸に流れ着いたとも言い伝える。このあたりは中世には長谷寺へ観音詣でする人たちでにぎわった。
仏教伝来碑
記紀の記述や万葉集の歌で名高い海石榴市は、三輪山麓南西方向の金屋周辺と推定されている。東西南北からの重要な街道が交差し、大和川を上り下りする船の起点となった。市が立ち、歌垣が催され、大陸からの賓客を迎える玄関であった。仏教が初伝来したという552年(あるいは538年)、時の欽明天皇の宮がこのあたりにあったとされることから、仏像と経論を携えた百済聖明王の使者も上陸の第一歩をこの地に印したのだろうか。付近の河原は公園として整備された。
磯城島金刺宮(しきしまかなさしのみや)跡碑
日本書紀には「欽明天皇元年に都を倭国の磯城郡の磯城島に遷す。よりてなづけて磯城島金刺宮とす」とある。金刺宮の正確な所在地は特定されていないが、現在は市の水道局となったこの場所に宮跡碑が建つ。
椿山
海石榴市の地名の元になった椿の故事にならって、上田重治郎氏が所有の山に椿を植え育て続けている。椿が咲く二月から五月まで一般見学で山を開放する。頂上からは
大和三山や葛城山地の眺望がすばらしい。
玉列(たまつら)神社
大神神社の摂社で、「玉椿大明神」と呼び親しまれている。境内にはヤブ椿が群生する。
脇本遺跡
朝倉小学校から付近の田畑一帯の発掘調査で、石組みの排水溝を含む五世紀後半の宮殿遺構が発見された。日本書紀にある雄略天皇の泊瀬(はつせ)朝倉宮跡と推定されている。
白山(しろやま)神社
境内には保田與重郎氏揮毫の「萬葉集発耀讃仰碑」と雄略天皇御製歌歌碑が建つ。付近に雄略天皇の泊瀬(はつせ)朝倉宮があったとされ、御製歌が萬葉集の巻頭を占めることによる。 |