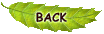登る苦労は何処へやら |
 楽しい山頂オペレート |
 運用終わって爽快感満点 |
| 山頂での7MHz移動運用 目指しているところ | |
| 平日に土日V・UHF移動と、同レベルの交信数を楽しみたい 平日の日中に、多くのQSOを楽しめるバンドは、それほど多くはありません。 7MHzSSBなら、多くの方が運用しています。このバンドモードを利用して、山頂で積極的にCQを出して、呼んで貰える移動運用をしたいのです。 | |
| 平地と違わない移動運用をしたい これまで7MHzSSBは、車で運用地に行き、大がかりな設備を使用していました。賑やか故に混信が多く、ミニパワーでのSSB運用は、難しいとされています。山頂でも、今まで楽しんできた移動運用と、違わない運用を楽しみたいのです。 | |
| 山登り、移動運用、両方楽しみたい 移動運用も好きですが、山登りも好きです。2つを同時にすると、満足度は2倍です。徒歩で無理なく運べる、軽量な設備を持って行き、移動運用を楽しみたいのです。 |
 登る苦労は何処へやら |
 楽しい山頂オペレート |
 運用終わって爽快感満点 |
| 運用設備について その1 | |
| 7MHz運用が出来るトランシーバー
FT817 FT817を5W出力で利用しています。1.9MHzから430MHzまで、多くのバンド、モードで運用できます。エレキーも内蔵されていて、パドルをつなぐだけで、快適なCW運用が可能なトランシーバーです。オプションの500HzのCWフィルターを装着しています。CW愛好局は購入をおすすめします。 | |
| トランシーバー動作用電源 市販ポータブル電源(6000円程)を利用しています。本体内に、シールドバッテリー(8Ah)が入っています。 5WでフルタイムCQを出し続けて、5時間の運用が可能です。予備電源として、充電可能な単3型Ni-MH電池8本を内蔵しています。充電し終えて、電池の間に1枚フィルムを挟んでいます。 FT817は、電池を入れているだけで、微量の電流が流れているため、電池が消耗します。肝心なときにきちんと使えるように、内蔵させてはいても消耗しないようにしています。 | |
| 小物類 ログは手書き記入しています。リュックに入れていると、雨や汗で濡れたりするのを防ぐために、ビニルケースに入れて持ち歩きます。時刻確認は、安物の腕時計をFT817のキャリングベルトに付けておいて使っています。時計を忘れる事がなく重宝しています。運用道具一式を、100円ショップで購入した、靴袋2つに納めています。 CW運用時のパドルには、GHDキー社の「GM307WS」を利用しています。これだけ特別に、保護用ソフトポーチに入れたあとで、靴袋に入れています。 |
 ベンチが無線室です |
 5時間以上CQ出せます |
 小型パドルでCW運用も可能 |
| 運用設備について その2 アンテナ | |
| アンテナ 全長約10mの半波長ダイポールアンテナを5mポールで設営します。バランは、コメット社のものを利用し、同軸は3D-2V 7mです。 7MHz用ダイポールアンテナは、21MHzの電波も送受信することが出来ます。コンディションが悪いときに、7MHz以外が運用できるのは、心強いことです。 | |
| 設営用具 ポール固定にクランプを利用して、設営時間を短縮しています。山頂の工作物と、ポールをクランプで一緒に挟んで、ポールを垂直に立てます。クランプ以外にも、10mクレモナロープを2本準備しており、状況によって利用します。ポールとアンテナバランの固定は、塩ビパイプを利用しています。塩ビパイプに、ねじでバランを固定して、ポールに被せています。金属製のポールと、アンテナとの干渉を幾らかでも少なくしたいためです。 | |
| アンテナ設営 山頂は、広い場所ばかりではなく、樹木で覆われている場所があります。設営時は、SWRが極端に悪くなるため、バランから1mまでのエレメントに、障害物が触れないようにしています。それ以外でも、エレメントに障害物があたらないように設営しています。 | |
| こだわり 50Wでも厳しい事がある7MHz運用です。 5Wミニパワー運用をするのですから、電波の飛びに良さそうな事をアンテナに取り入れました。重くなりましたが、ちゃんとしたエレメント線とバランを採用しました。本当は、山登りの体力との相談もあり、軽量化できるならしたいのです。しかしアンテナは、軽量化を考えない事にしました。これが私のこだわりです。 調整も、中心周波数が7.03MHzにくる様にしました。長めのままなら、21MHzもSWRを落とせましたが、余分は切ってしまいました。 7MHzで完璧な調整をしていれば「アンテナが原因で飛ばない」と、云う事がありません。呼ばれなかったとすれば、他に原因があると、考えることが出来ます。山頂では、体力を消耗していて余裕がないので、考える事は少しでも減らしたい。これが私のこだわりです。 |
 7MHzDPは21MHzも利用可能 |
 クランプで簡単設営 |
 塩ビパイプで簡単固定 |
| 運用周波数について | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 7MHzアマチュアバンド周波数区分 運用経験を基に、大雑把な周波数区分表を作りました。バンド内は刻々と変化します。必ずあてはまる訳ではありません。そのつもりで参考にして下さい。ミニパワーでの運用周波数は、ぴったりの周波数(例 7.050MHzや7.055MHz)よりも、少しずれた周波数 (例 7.0505MHz 7.0555MHz)の方が、応答がよくなる気がします。 | ||||||||||||||||
| 運用方法 | |
| 「短い」が重要 短いCQを短い間隔で出す事が、ミニパワー運用では、重要に感じます。「CQ CQ CQ こちらはJL3TOGポータブル3 山頂移動です 受信します」これを短間隔(5秒以内)で出し続けます。長いCQの間に、別の局がCQを出し始めたなんて事があります。短い方が、間違いなく応答は良いです。 | |
| 聞き取りやすい声を出す 聞き取って貰いやすいように、ハキハキした声を出す様に心掛けています。元気のあるCQは、周波数ダイヤルを回している手を止める力があるようです。 | |
| 空振りCQを苦にしない ミニパワー運用は、簡単には呼んで貰えません。20回ぐらいの空振りCQは、当たり前だと思って運用した方がいいです。カラオケに行って、歌っている気になってCQを出すと、気分良く続けることが出来ます。 | |
| 混信が強ければ周波数を変える 空振りCQが続くとき、原因が強力な混信の場合は、周波数を変えましょう。ミニパワー運用局は、ちょっとした混信でも、探して貰い難いものです。弱い混信なら、我慢して頑張ってみましょう。 | |
| 交信時のひと工夫 強力な局から1局だけ応答があったときは、長く話して貰う工夫をしましょう。強い局が長く話してくれると、多くの局に運用を知らせることが出来ます。ミニパワーの自分は、長く話さないのが呼んで貰うコツです。本来は、多くの方から応答があった場合は、テキパキ交信を終えるのがマナーです。 | |
| 特殊な運用をアピール ミニパワー運用、山頂運用を嫌みのない程度、QSOに織りまぜると、応答率が上がるような気がします。「FT817での運用」で、FT817ユーザーが3局続いた事がありました。「5W運用」で、7MHzでミニパワーCQに驚いた受信局で、パイルアップが出来ました。「○○山移動」で、設備に興味を持った局から呼んで貰い、問い合わせQSOになりました。 |
 短いCQで応答アップ |
 山の雰囲気を伝えるも良し |
 自慢話も応答アップのコツ |
| 寄せられた疑問と今後の課題 | |
| ハムフェアー2004で小冊子にして配りました ハムフェアー2004会場にて、このページをコピーしてつくった小冊子を無料配布しました。そのときに、読んで頂いた方から頂いた感想や、生まれた疑問を私なりに回答してみました。 | |
| 山頂で7MHz移動運用をするメリットは? 7MHzは、谷間などのロケの悪い場所でも、運用できる周波数です。わざわざ山頂で、運用する必要があるのだろうかと、訊ねられました。 V/UHF帯での運用時には、ごく近所である5〜15Kmの範囲にいる局との交信は、当たり前に出来るのに対して、平地での7MHz運用の時、この範囲の局との交信は、あまりする事が出来ません。しかし、山頂での運用では、7MHzでの運用でもこの範囲の局との交信が、容易に行うことが出来ます。見通しの良い場所での運用は、7MHzでは皆無のグランドウェーブ伝搬を楽しむことが出来て、不思議な体験をさせてくれます。 | |
| 軽量化しないの? 軽量化は、今後図っていきたいです。山頂を目指すとき、荷物は軽いにこした事はありません。行き過ぎた軽量化は、沢山の方と交信したいとはじめた、この運用目的を阻害することになりかねません。多少の重さは、体を鍛えるという別の目的のためと、自分に言い聞かせて、我慢するようにしたいと思います。 |